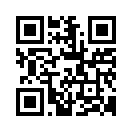2011年03月23日
歌のチカラ!
私の大好きな曲です。
元気と勇気が湧く曲です!
聴いてください!
http://www.youtube.com/watch?v=ApT0SdqjhHg
「新しい船」
いつもお世話になっている、魂のヴォーカリスト“直@坊”さんたちが歌っています。
音楽っていいですね♪

カラーセラピー・カラーオブハート ◇~Color Of Heart~◇
元気と勇気が湧く曲です!
聴いてください!
http://www.youtube.com/watch?v=ApT0SdqjhHg
「新しい船」
いつもお世話になっている、魂のヴォーカリスト“直@坊”さんたちが歌っています。
音楽っていいですね♪
カラーセラピー・カラーオブハート ◇~Color Of Heart~◇
タグ :新しい船
2011年03月23日
災害・緊急時、大事にしたい話し方・伝え方。(抜粋して転載)
震災よりもうすぐ2週間。
そろそろ疲れも出てきたり、イライラしやすかったりする時期です。
とてもいい記事を見つけましたので、mixiニュースより抜粋して転載いたします。
***************
東北地方太平洋沖地震で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
今回被害の少なかった地域でも、まだ緊張感や不安が続いています。家族や親戚、知人などが被災された方もいらっしゃるでしょう。いたわりの言葉が救いになることがある一方で、ストレスの強い状況下では、伝え方がうまくできないために傷つけ合ってしまうこともあります。災害時という特殊な状況での行動の仕方を、話し方・伝え方の見地からご紹介しますので参考になさってください。
■子供に安心を伝える
余震や原発の問題などで不安な時期ですが、親が動揺していると子供も不安定になってしまいます。明るい言葉をかけるなど、笑顔を見せる、抱きしめるなどの非言語コミュニケーションを多く使いながら子供に安心を伝えてあげてください。抱きしめるという行為は、心のケアにもいいとされています。
被害の少ない場所にいる方も報道が気になる時期ですが、テレビのつけっぱなしはやめましょう。視覚を使った情報伝達の有効性を考えると、子供に被災のシーンを繰り返し見せるのは避けた方が賢明です。私達は言葉以外の部分でもコミュニケーションをとっています。行動や雰囲気からも多くの情報が伝わりますので非常時の家族のルール(行動の仕方、集合場所等)を確認したら、子供の前ではいつもどおりを演出するくらいの気持ちで接することをお勧めします。
阪神淡路大震災や新潟中越地震の際には、地震や停電を経験したことで、急に暗いところを怖がるようになってしまった、情緒が不安定になってしまった、おむつに戻ってしまったなどの事例も報告されています。ついつい漏らしがちな、ネガティブな言葉も子供の前では我慢し、なるべく安心を伝えるよう心がけましょう。
■人間心理と声かけの効果
私達は他者と自分の間のバランスを求め、公平である状態を好みます(こういう状態を心理学では「衡平理論」といいます)。そのため、物資の分配や我慢の分配がうまくいかない状態では大きな不快感を感じるでしょう。しかしながら、共有する有限なものを前にすると利己的な考え方をしてしまう心理も働きます。みんなの利益のために行動するか、個人の利益のために行動するかの葛藤が生まれてしまうのです(こういう状態を心理学では「コモンズのジレンマ」といいます)。
そんな状況の中で、助け合うためには「声をかけ合う」「話し合う」ことが有効です。研究では、話し合いや情報交換、ルールなどによって協力行動が促されると報告されています。周囲の協力が得られるという期待感を持てるようになると、事態を好転させることが可能になるのです。ギスギスした環境では、いろんな気持ちが芽生えてしまうのも当たり前。そんな時に自分や他者を責めてはいけません。隣の人に声をかけ、コミュニケーションをとり、助け合いの土壌を作ることで事態を好転させましょう。
■いたわりの声をかけあおう
被災された方、自分は無事でも親戚や知人が被災した方など、震災によって心に傷ができてしまった人も少なくないと思います。どんどん周りの人を気遣う言葉をかけ合いましょう。
今回インタビューをさせてくれた阪神淡路大震災の被災者の方は「震災も仮設での生活もつらかったけれど、ボランティアの人に話を聞いてもらえて気分が少し落ち着いた」とおっしゃっていました。特に女性は、話すという行為でストレスを緩和しやすいと言われています。「大丈夫だった?」「つらくない?」などの声掛けをし、相手が話をしやすいきっかけを作るようにしていきましょう。
■「頑張れ」の使い方に注意
一般的によく使われる「頑張れ」という言葉は、「これ以上どうやって頑張ればいいのだろう?」と受け取られてしまうこともあるので注意が必要です。つらい人に対しては、励ましよりも「聴く」に軸足を置くコミュニケーションをとるようにしたほうがいいでしょう。相手の話を聴き、心を寄り添わせる行為自体が励ましになります。言語だけがコミュニケーションではないことを思い出しましょう。
震災が起きてしばらくすると、被害のない地域にいる人達にも「何もできない自分」というストレスがかかることがあります。あなたの周りにも無力感にさいなまれ、もどかしい思いをしている人もいるかも知れません。そういうストレスを感じた場合には、ぜひ「聴く」という貢献をしていただきたいと思います。普通に振る舞っている人の中にも、親戚や知人が被災して苦しさを抱えている人がいるかも知れません。そういった人に気遣い、心を寄り添わせるのも立派な貢献なのです。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1542800&media_id=77
***************
被災生活13日目。
いろいろな想いがありますが、特に小さいお子さんたちは私たち大人が守ってあげないとですね!
今日も愛でいっぱいに 。
。

カラーセラピー・カラーオブハート ◇~Color Of Heart~◇
そろそろ疲れも出てきたり、イライラしやすかったりする時期です。
とてもいい記事を見つけましたので、mixiニュースより抜粋して転載いたします。
***************
東北地方太平洋沖地震で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
今回被害の少なかった地域でも、まだ緊張感や不安が続いています。家族や親戚、知人などが被災された方もいらっしゃるでしょう。いたわりの言葉が救いになることがある一方で、ストレスの強い状況下では、伝え方がうまくできないために傷つけ合ってしまうこともあります。災害時という特殊な状況での行動の仕方を、話し方・伝え方の見地からご紹介しますので参考になさってください。
■子供に安心を伝える
余震や原発の問題などで不安な時期ですが、親が動揺していると子供も不安定になってしまいます。明るい言葉をかけるなど、笑顔を見せる、抱きしめるなどの非言語コミュニケーションを多く使いながら子供に安心を伝えてあげてください。抱きしめるという行為は、心のケアにもいいとされています。
被害の少ない場所にいる方も報道が気になる時期ですが、テレビのつけっぱなしはやめましょう。視覚を使った情報伝達の有効性を考えると、子供に被災のシーンを繰り返し見せるのは避けた方が賢明です。私達は言葉以外の部分でもコミュニケーションをとっています。行動や雰囲気からも多くの情報が伝わりますので非常時の家族のルール(行動の仕方、集合場所等)を確認したら、子供の前ではいつもどおりを演出するくらいの気持ちで接することをお勧めします。
阪神淡路大震災や新潟中越地震の際には、地震や停電を経験したことで、急に暗いところを怖がるようになってしまった、情緒が不安定になってしまった、おむつに戻ってしまったなどの事例も報告されています。ついつい漏らしがちな、ネガティブな言葉も子供の前では我慢し、なるべく安心を伝えるよう心がけましょう。
■人間心理と声かけの効果
私達は他者と自分の間のバランスを求め、公平である状態を好みます(こういう状態を心理学では「衡平理論」といいます)。そのため、物資の分配や我慢の分配がうまくいかない状態では大きな不快感を感じるでしょう。しかしながら、共有する有限なものを前にすると利己的な考え方をしてしまう心理も働きます。みんなの利益のために行動するか、個人の利益のために行動するかの葛藤が生まれてしまうのです(こういう状態を心理学では「コモンズのジレンマ」といいます)。
そんな状況の中で、助け合うためには「声をかけ合う」「話し合う」ことが有効です。研究では、話し合いや情報交換、ルールなどによって協力行動が促されると報告されています。周囲の協力が得られるという期待感を持てるようになると、事態を好転させることが可能になるのです。ギスギスした環境では、いろんな気持ちが芽生えてしまうのも当たり前。そんな時に自分や他者を責めてはいけません。隣の人に声をかけ、コミュニケーションをとり、助け合いの土壌を作ることで事態を好転させましょう。
■いたわりの声をかけあおう
被災された方、自分は無事でも親戚や知人が被災した方など、震災によって心に傷ができてしまった人も少なくないと思います。どんどん周りの人を気遣う言葉をかけ合いましょう。
今回インタビューをさせてくれた阪神淡路大震災の被災者の方は「震災も仮設での生活もつらかったけれど、ボランティアの人に話を聞いてもらえて気分が少し落ち着いた」とおっしゃっていました。特に女性は、話すという行為でストレスを緩和しやすいと言われています。「大丈夫だった?」「つらくない?」などの声掛けをし、相手が話をしやすいきっかけを作るようにしていきましょう。
■「頑張れ」の使い方に注意
一般的によく使われる「頑張れ」という言葉は、「これ以上どうやって頑張ればいいのだろう?」と受け取られてしまうこともあるので注意が必要です。つらい人に対しては、励ましよりも「聴く」に軸足を置くコミュニケーションをとるようにしたほうがいいでしょう。相手の話を聴き、心を寄り添わせる行為自体が励ましになります。言語だけがコミュニケーションではないことを思い出しましょう。
震災が起きてしばらくすると、被害のない地域にいる人達にも「何もできない自分」というストレスがかかることがあります。あなたの周りにも無力感にさいなまれ、もどかしい思いをしている人もいるかも知れません。そういうストレスを感じた場合には、ぜひ「聴く」という貢献をしていただきたいと思います。普通に振る舞っている人の中にも、親戚や知人が被災して苦しさを抱えている人がいるかも知れません。そういった人に気遣い、心を寄り添わせるのも立派な貢献なのです。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1542800&media_id=77
***************
被災生活13日目。
いろいろな想いがありますが、特に小さいお子さんたちは私たち大人が守ってあげないとですね!
今日も愛でいっぱいに
 。
。カラーセラピー・カラーオブハート ◇~Color Of Heart~◇